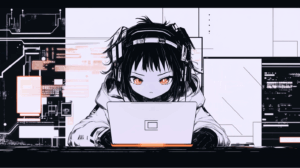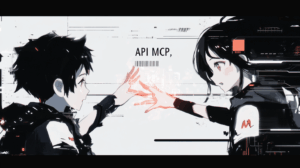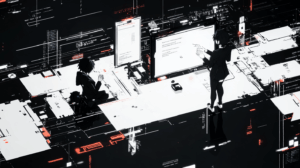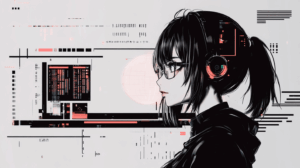著者:GOZEN AI Lab管理人
生成AIエンジニア(オープンバッジ取得)生活や業務に潜む「面倒くさい」を手放すため、生成AIを活用した業務効率化施策、自動化ワークフローの構築・運用などを手がけ、実践と継続的な改善を通じて仕組みづくりを推進している。
結論:AIツールを使いこなせば、あなたの「困った」が一瞬で「できた!」に変わる。
近年、様々な「AIツール」が登場しており、「文章を書いてくれるAI」「絵を描いてくれるAI」「面倒な作業を自動でやってくれるAI」など、その種類は本当に豊富。ツール迷子になる位、これからも新しいツールが出てくるでしょう。
この記事では、そんなあなたの悩みを解決するため、様々な「目的別 AIツール」を分かりやすくご紹介します。「こうなったらいいな」と思っていることをAIがどう実現してくれるのか、具体的なイメージを持って読んでいただけると嬉しいです。
専門的な知識は一切不要なので「なんか難しそう…」と思っている方にも理解できるように、かみ砕いて解説していきます。ぜひ最後まで読んで、あなたの困り事を解決するAIツールを見つけてください。
AIツールでできること:目的別ガイド
AIツールと一口に言っても、その活用範囲は驚くほど広く、私たちの手助けをしてくれるAIは、様々な分野で活躍しています。
主な活用目的をいくつかご紹介しましょう。
- 「書く」をもっと楽にしたい: 文章作成、メール返信、企画書のドラフト、ブログ記事のアイデア出し…
- 「作る」をもっと自由にしたい: 絵やイラスト、デザインのラフ、動画、音楽、プレゼン資料…
- 「調べる・学ぶ」をもっと効率的に: 知りたいことの要約、資料の翻訳、プログラミングコードの解説…
- 「仕事・作業」を自動化したい: 会議の議事録作成、データ分析、スケジュール調整…
このように、あなたの「困った」や「もっとこうしたい」という想いを形にするためのAIツールが必ず存在します。次からは、これらの目的ごとに、どんなAIツールがあるのか、具体的に見ていきましょう。
【あなたの目的はどれ?】おすすめAIツールを徹底解説
文章作成・要約の効率アップに
「メールの返信が面倒くさい」「ブログ記事のアイデアが浮かばない」「会議の議事録を短くまとめたい」…こんなお悩み、ありませんか?
文章作成 AIは、これらの「書く」「まとめる」作業を強力にサポートしてくれます。キーワードや箇条書きを与えるだけで、自然な文章を作成したり、長い文章をあっという間に要約したりすることが得意です。
例えば、
- 顧客への丁寧なメール返信案を瞬時に作成
- 会議中の発言をリアルタイムで文字起こし&要約
- ブログ記事の構成案や見出しを提案
- 新しい企画のアイデア出しの壁打ち相手として
といった使い方が考えられます。
代表的なツールとしては、ChatGPTやGoogleのGemini、Notion AIなどがあります。これらのツールは、まるで有能なアシスタントのように、あなたの「書く」作業時間を大幅に短縮してくれるでしょう。
 筆者
筆者個人的に私が使用しているのは、文章作成は『Gemini』要約は『ChatGPT』です。
何故、使い分けているのかというと、Geminiは文を書くのが非常に上手で、私のやりたい事や趣味嗜好を最適化する事が得意なのはChatGPTだからです。
別にこのように使い分けなくてもどちらも文句なしの性能を持っていますので「好み」位の感覚でOKです!
また、詳細なプロンプトでAIに指示する事でさらに高品質な出力が可能です。
詳しい解説やAIの選定方法等はこちらの記事でさらに詳しく解説しています。


クリエイティブなアイデアを形に!画像生成・編集
頭の中にあるイメージを絵やデザインとして表現したい。でも、絵心がないし、デザインソフトも使えない…そんな時こそ、画像生成 AIの出番です。
「夕焼けの海辺を歩く犬」とか、「サイバーパンクな街並み」のように、言葉でイメージを伝えるだけで、AIがそれに合った画像を生成してくれます。既存の画像を編集したり、特定のスタイルで加工したりすることも可能です。
使い道は多岐にわたります。
- プレゼン資料や企画書に使うイメージ画像を手軽に用意
- SNS投稿用の目を引くオリジナル画像を作成
- ウェブサイトやブログのデザインラフを素早く試作
- 自分が思い描くファンタジー世界のビジュアル化
といったことが、専門的なスキルがなくてもできるようになります。
Midjourney、DALL-Eなどが有名な画像生成 AIツールとして挙げられます。これらのツールを使えば、あなたのクリエイティブな発想がどんどん形になっていくのを実感できるはずです。
こちらも、詳細なプロンプトでAIに指示する事でさらに高品質な出力が可能です
また、活用事例や注意点はこちらで詳しく解説しています。


動画をもっと手軽に!動画編集・生成
YouTubeやSNSで動画を発信したい、会社の紹介動画を作りたい、でも編集ソフトは複雑そう…
動画編集も、AIの力でぐっと身近になっています。AIが自動でハイライトシーンを選んでくれたり、BGMやテロップを付けてくれたり、さらにはゼロから動画を生成してくれるツールまで登場しています。
例えば、
- 撮影した動画素材をアップロードするだけで、編集済みの動画が完成
- テキストを入力するだけで、まるで人が話しているようなナレーション付き動画を生成
- プレゼン資料を元に、説明動画を自動作成
RunwayMLやSynthesia、PixVerseといったツールが、動画制作のハードルを下げてくれます。プロ並みの動画を手軽に作りたい、という目的に応えてくれるAIツールです。
こちらも詳細なプロンプトでAIに指示する事でさらに高品質な出力が可能です。
また、英語でのプロンプト入力を求められる傾向にありますが、それもChatGPTなどに「〇〇で、こんな感じの動画が作りたいから〇〇みたいなイメージのプロンプトを出してください」と依頼すれば簡単です。



私はがっつり動画編集する事はないので、PixVerseで素材を作ってもらえるのがとても助かっています。例えばですが、「Midjourneyで画像を生成し、それを動かす」といった事が出来ます。
このサイトのホームで最初に軽い動画が流れていますが、あのような感じです。
オリジナルの音楽を作曲!音楽生成・編集
動画のBGMが欲しい、自分のポッドキャストにオリジナルのテーマ曲を付けたい、作曲って難しそう…
音楽生成 AIは、あなたのイメージに合わせて音楽を作り出してくれます。「明るい雰囲気のジャズ」「壮大なオーケストラ」「元気が出るポップス」のように、ジャンルや雰囲気を伝えるだけで、AIが作曲してくれます。
用途例:
- 自作動画やプレゼンにぴったりのBGMを生成
- 作曲のインスピレーションを得るための素材作り
- 自分だけのプレイリスト作成
Suno AIやUdioなどが、言葉や簡単な指示から音楽を生み出すツールとして注目されています。音楽の知識がなくても、あなただけのオリジナル楽曲を持つことができるAIツールです。Suno AIの場合「歌詞を作成してそれを歌ってもらう」等もできますが、その場合、曲に対してのプロンプトと「歌詞」のイメージが楽曲に反映されるので、ガチャ要素も強いですが、感動する事は間違いないです。
プログラミングやコードもAIにお任せ?コード生成・デバッグ
「プログラミングを始めたいけど、どこから手をつけていいか分からない」「書いたコードにエラーがあるみたいだけど、どこが間違っているんだろう?」
プログラミングは専門知識が必要で難しそう…そんな印象があるかもしれません。しかし、AIはコードを書く手助けもしてくれます。
AIに「こんな機能を持つプログラムを書きたい」と伝えれば、コードのひな形を生成してくれたり、書いたコードの間違い(バグ)を見つけて修正方法を提案してくれたりします。
「〇〇のアプリを作って」と指示すればアプリが完成してしまう程、高性能なものもあります。
- 作りたい機能のコードを提案してもらう
- エラーが出たときに原因や修正方法を聞く
- 初めて触れるプログラミング言語のコードを解説してもらう
CursorやGitHub Copilotや一部のチャットAIなどが、プログラミングの学習や効率化をサポートするツールとして活用されています。



例えばGASでWEBアプリを作ったり、マクロ等のコードも書いてくれたりするので、普段Excel等を使っている人も知っておいて損はないと思います。私がAIに最初に触れたきっかけは「マクロを作ってもらいたかった」から始まりました。
また、詳しい解説はこちらでもしています。
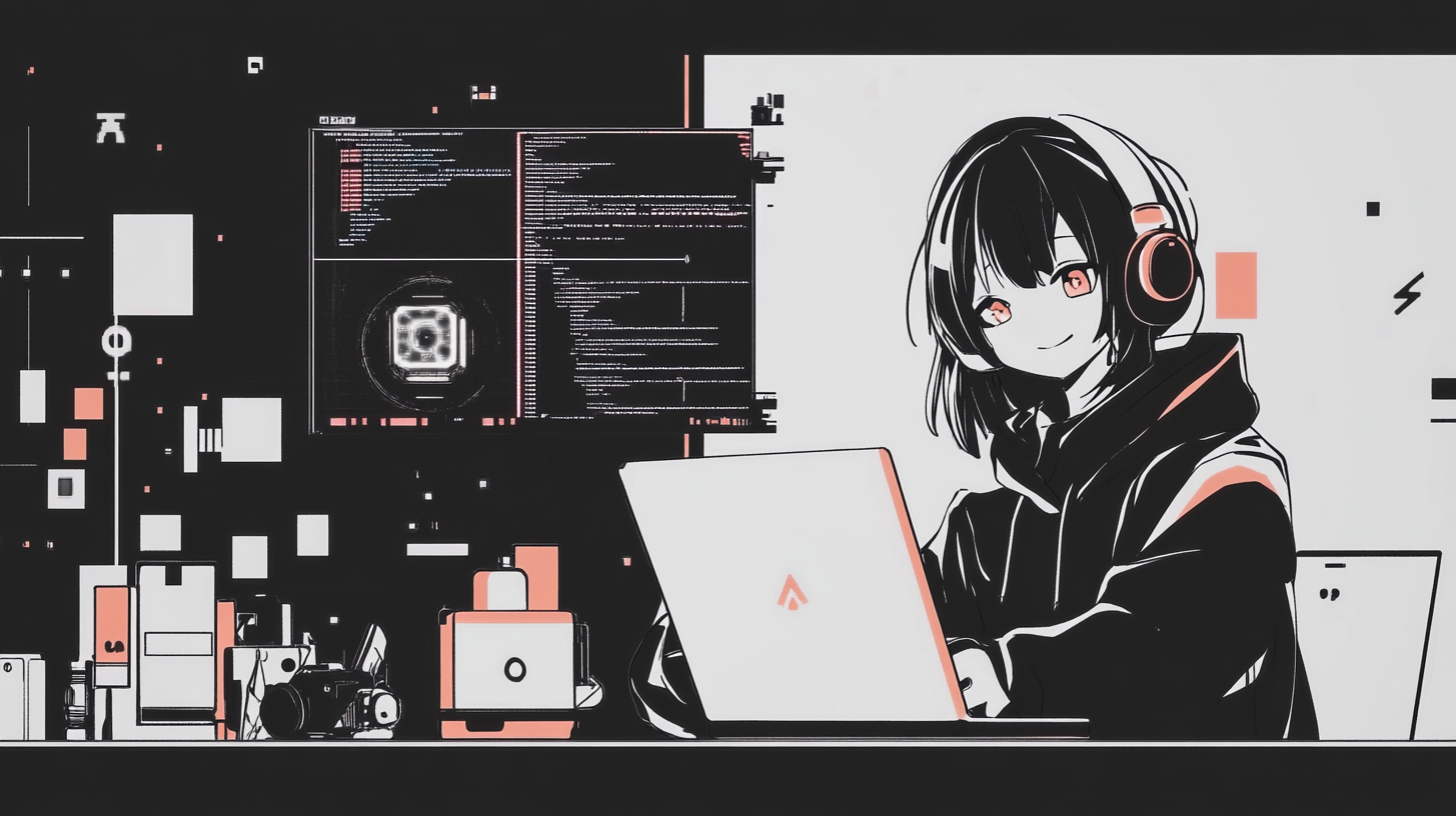
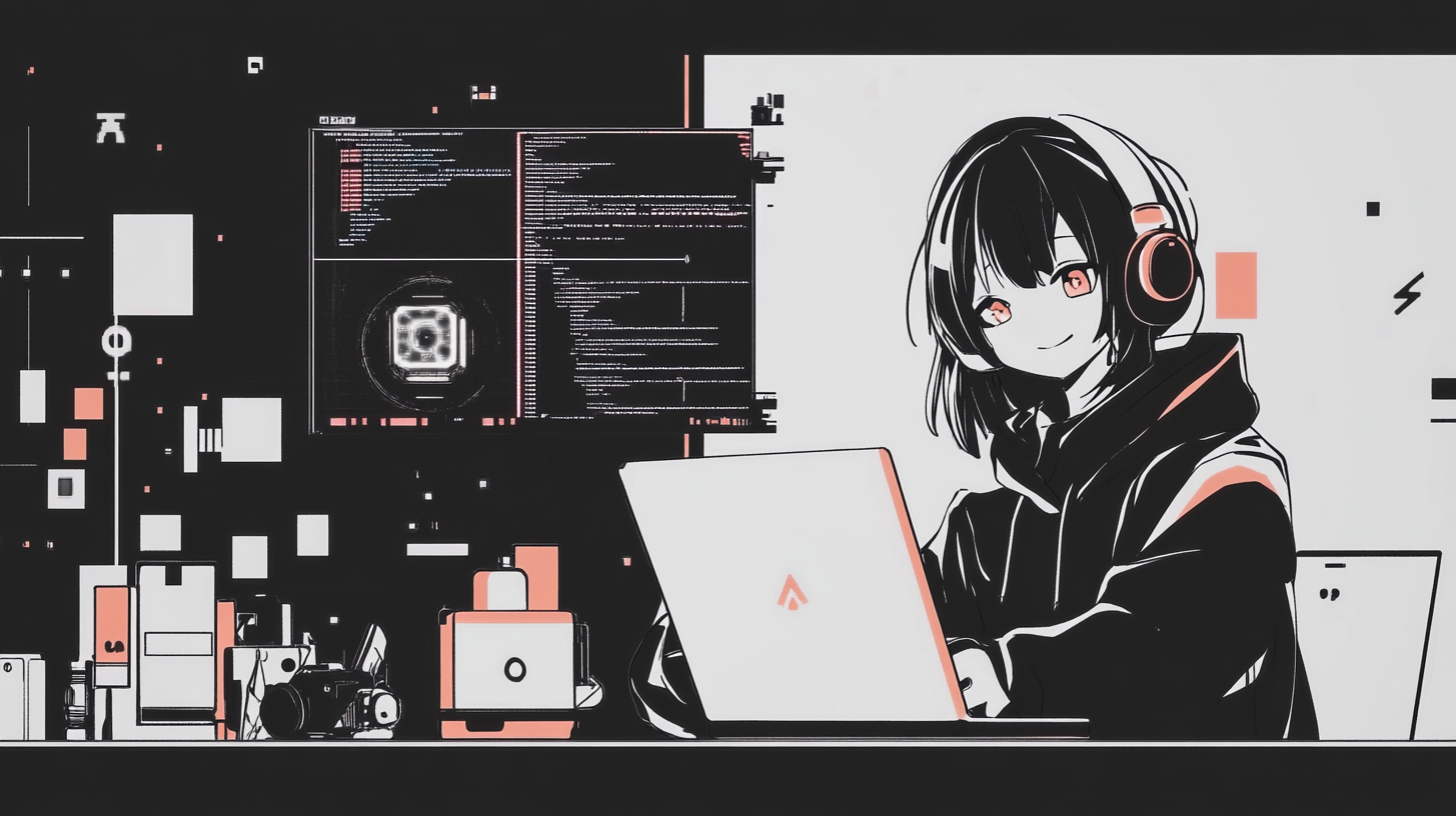
言葉の壁をなくす!翻訳・多言語対応
海外の人とコミュニケーションを取りたい、外国語の資料を読みたい、でも語学は苦手…
翻訳AIは、もはや私たちの生活に欠かせないものになっています。以前と比べてその精度は格段に向上し、専門的な内容やニュアンスもかなり正確に翻訳できるようになりました。
- 外国語のメールやチャットを瞬時に理解する
- 海外のウェブサイトの情報を正確に把握する
- 外国語でのコミュニケーションを円滑にする
DeepLやGoogle翻訳は、多くの人が利用している代表的な翻訳AIツールです。これらのツールを使えば、世界の情報を手に入れたり、国境を越えたコミュニケーションがずっと簡単になります。
学習や調べ物をサポート!教育・学習支援
「分からないことを誰かに分かりやすく教えてほしい」「大量の資料を効率的に学びたい」
学習の場面でも、AIツールは強い味方になります。質問に答えてくれたり、長い教科書や論文を要約してくれたり、個々の学習ペースに合わせた課題を提案してくれたりします。
- 学校の授業で分からなかったことをAIに質問
- 読まなければいけない長いレポートを要約してもらう
- 語学学習のパートナーとして会話練習をする
NotebookLMなどを活用することで、個別指導を受けているかのように学習を進めることができます。



例えば、NotebookLMではウェブサイトやYouTube、Googleドライブの資料、などを簡単に取り込むことができますので、海外のツールを使っていてドキュメントが全部英語・・・という場合でもツールの説明があるURLをコピペするだけで、ナレッジができます。
また、DeNAの南場会長は、商談前などに相手の情報をNotebookLMにいれ、要約する等して活用されているようです。
日々の業務を効率化!ビジネス・仕事効率化
「定型的なメール作成に時間がかかる」「会議中にメモを取るのが大変」「タスク管理をもっとスムーズにしたい」…
日々のビジネスシーンには、AIツールで効率化できる作業がたくさんあります。
- 会議中の会話をリアルタイムで文字起こしし、自動で議事録を作成
- 過去のメールのやり取りを学習して、最適な返信案を提案
- 煩雑なデータ入力を自動化
- 書類の内容を理解して必要な情報を抽出
議事録ツールやAIエージェントは、あなたの時間を生み出し、よりクリエイティブで重要な業務に集中することを可能にしてくれます。
またこちらの記事でも初心者向けに解説していますのでよかったら見てください。


【迷ったらここを見る!】あなたにぴったりのAIツールの選び方


さて、様々な目的別 AIツールがあることが分かりました。でも、たくさんありすぎて、どれを選べばいいか迷ってしまいますよね。ここではあなたにぴったりのツールを見つけるための簡単なステップをご紹介します。
- ステップ1:まずは「何のために」AIを使いたいかを明確に
これが最も重要です。「文章を書きたい」「絵を作りたい」「仕事を効率化したい」など、まずは一番解決したい課題や達成したい目的を一つに絞ってみましょう。目的が明確になれば、探すべきツールの種類がおのずと見えてきます。 - ステップ2:機能と性能はあなたの目的に合っているか?
目的が明確になったら、その目的に特化したツールや、目的を達成するために必要な機能(例:長文要約、高精度な画像生成、特定のファイル形式への対応など)を持っているかを確認しましょう。デモ動画を見たり、無料トライアルを利用してみるのも良い方法です。 - ステップ3:使いやすさ、始めやすさも大事
どんなに高性能なツールでも、使い方が複雑すぎると挫折してしまいます。画面は分かりやすいか、操作は直感的か、日本語に対応しているかなども確認しましょう。特にAIツールが初めての方は、シンプルで分かりやすいデザインのものがおすすめです。 - ステップ4:無料プランはある?料金体系は?
まずは試してみたい、という方にはAIツール 無料プランがあるかどうかが重要です。無料プランで試してみて、自分の目的に合うと感じたら有料プランへの移行を検討しましょう。有料プランの料金体系(月額、年額、従量課金など)も、継続して使うことを考えて確認しておきましょう。AIツール 無料で始められるものは、気軽に第一歩を踏み出すのに最適です。 - ステップ5:困ったときのサポートはある?
新しいツールを使っていると、疑問やトラブルはつきものです。困った時にヘルプドキュメントが充実しているか、サポートに問い合わせできるかどうかも、安心して使うためには確認しておきたいポイントです。
これらのステップを踏むことで、あなたに最適な目的別 AIツールが見つけやすくなるはずです。
AIツール活用の明るい未来と知っておきたい注意点
AIツールを使いこなすことで、私たちの可能性は大きく広がります。
- 時間短縮: 面倒な作業や時間がかかる作業をAIに任せることで、他の重要なことに時間を使えるようになります。
- コスト削減: 専門家でなければ難しかった作業も、AIツールを使えば自分自身で、あるいは少ないコストで実現できます。
- 新しい発想: AIは時に人間では思いつかないようなアイデアや解決策を提示してくれます。
- 可能性拡大: スキルや知識がなくても、AIツールの助けを借りて新しいことに挑戦できるようになります。
ただし、AIツールを使う上でいくつか知っておきたい注意点もあります。
・情報の正確性: AIは学習データに基づいて応答するため、誤った情報や偏った情報を出力することがあります。特に重要な情報については、必ず自分で確認するようにしましょう。
・著作権やプライバシー: AIが生成した文章や画像には著作権の問題が発生する場合があります。また、個人情報や機密情報をAIツールに入力する際には、プライバシーや情報漏洩のリスクがないか注意が必要です。ツールの利用規約をよく確認しましょう。
・依存しすぎない: AIツールはあくまであなたの「アシスタント」です。AIの出力結果を鵜呑みにせず、自分の頭で考え、最終的な判断は自分で行うことが大切です。
これらの注意点を理解した上で賢くAIツールを活用すれば、毎日や仕事がもっと便利になります。
まとめ:目的別AIツールを使いこなして、あなたの可能性を広げよう
この記事では、「目的別 AIツール」を、文章作成から画像生成、仕事効率化まで、様々な角度から見てきました。
AIツールは「一部の専門家だけのもの」とは私は考えていません。むしろ「専門家のレベルまで自分立ちを引き上げてくれるもの」と考えています。「こんなことできたらいいな」「これをもっと楽にしたいな」という具体的な目的に応じて、誰もが手軽に使える時代ですので、どんどん恐れず使ってみてください。
もしあなたがまだAIツールを使ったことがないなら、まずは無料のAIツールから試してみるのがおすすめです。例えば、チャットAIに質問してみたり、簡単な画像を生成してみたり。思っていたよりもずっと簡単に使えることに驚くかもしれません。
この記事を参考に、皆さんが良いAIツールと出会えたら幸いです。
よくある質問:FAQ
Q1. AIツールは全くの初心者でも使えますか?
A1. はい、ご心配いりません。多くのAIツールは、専門知識がない方でも直感的に使えるようにデザインされています。言葉でやりたいことを伝えるだけで使えるチャットAIや、簡単な操作で画像や音楽を生成できるツールなど、様々なレベルのユーザーに向けたツールがあります。まずはAIツール 無料で試せるものから気軽に始めてみるのがおすすめです。
Q2. 無料のAIツールでも大丈夫ですか?
A2. 目的に応じて、無料でも十分に役立つAIツールはたくさんあります。例えば、簡単な文章作成やアイデア出し、ちょっとした調べ物などであれば、無料のチャットAIでも十分対応できる場合があります。ただし、より高度な機能を使いたい場合や、利用回数に制限なく使いたい場合は、有料プランを検討する必要があるかもしれません。まずはAIツール 無料版で試してみて、機能に満足できるか確認しましょう。
Q3. 使いたいAIツールが複数ある場合、どう管理すれば良いですか?
A3. AIツールは目的ごとに異なるものが多いため、複数のツールを利用するのは一般的です。ブラウザのブックマークを活用したり、タスク管理ツールに用途ごとに分類して登録したりする方法があります。最近では、複数のAIモデルをまとめて使えるサービスなども登場しており、今後さらに使いやすくなることが期待されます。
Q4. AIが出力した情報や作品は自由に利用できますか?
A4. AIが生成したコンテンツの利用については、各ツールの利用規約を必ず確認してください。商用利用が可能かどうか、クレジット表記が必要かどうか、著作権は誰に帰属するのかなどは、ツールによって異なります。特にビジネスや公開目的で利用する場合は、トラブルにならないよう注意が必要です。
Q5. AIツールを使う上で注意すべきことはありますか?
A5. AIツールの出力結果は完璧ではありません。特に事実確認が必要な情報については、必ずご自身で確認しましょう。また、個人情報や企業の機密情報を入力する際には、セキュリティ対策がしっかりとされているツールを選ぶなど、情報漏洩のリスクに十分注意する必要があります。
専門用語解説
- 生成AI (Generative AI): これまでのAIが「分析する」「判断する」ことが得意だったのに対し、生成AIは文字通り新しい文章や画像、音楽などのコンテンツを「生成する」ことができるAIのことです。まるで人間がクリエイティブな作業をするように、オリジナルのものを作り出すのが得意です。
- プロンプト (Prompt): AIに何か作業を依頼する際に、入力する指示や命令文のことです。例えば、文章作成AIに「〇〇についてブログ記事を書いて」と指示したり、画像生成AIに「夕焼けの海辺を歩く犬の絵を描いて」と指示したりする、その指示そのものをプロンプトと呼びます。AIの性能を引き出すには、このプロンプトの作り方が重要になります。
- LLM (大規模言語モデル): LLMは「Large Language Model」の略で、非常に大量のテキストデータを学習したAIモデルのことです。LLMは、文章の生成、翻訳、要約、質問応答など、人間の言葉に関わる様々なタスクを高い精度で行うことができます。ChatGPTやGeminiなど、多くの生成AIツールは、このLLMをベースとして開発されています。