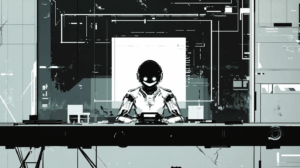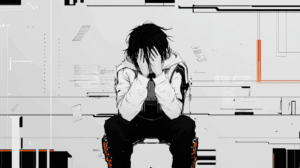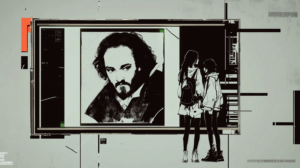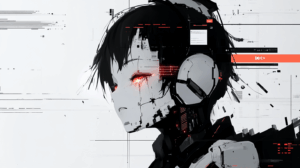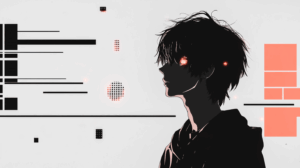著者:GOZEN AI Lab管理人
生成AIエンジニア(オープンバッジ取得)生活や業務に潜む「面倒くさい」を手放すため、生成AIを活用した業務効率化施策、自動化ワークフローの構築・運用などを手がけ、実践と継続的な改善を通じて仕組みづくりを推進している。
結論:「あいうえお」からの「んの絶望」まで…AIの狂気が詰まってた。
『AI実験シリーズ』第2弾の今回は「AIが作家になったらどのような物語を書くのか?」を検証してみました。
しかし、普通にやってもつまらないし、ガチでこられても冗長になるので、ルールをつけてみました。
そんな縛りプレイをAIに課してみたところ、
思った以上に“地獄の展覧会”が始まりました。
今回は、そんな狂気と詩情の間で震えるAIの物語生成実験を、ぜひお楽しみください。
検証プロンプト:サンプル
以下をそのままクエリとした訳ではないですが、参考までに「このようなプロンプトで出力してもらいました」の例です。
以下の制約条件と指示に従って、短編物語を生成してください。
* **制約条件:** 「物語の各段落または文章の冒頭が、ひらがな50音順に始まるようにする」
* **指示:**
* 物語の中に、一見すると滑稽でありながら、深く考えると人間の悲哀や愚かしさを象徴するような要素を織り交ぜてください。読者が最初は笑ってしまうかもしれないが、後になってその裏に潜む痛みに気づくような仕掛けを期待します。
* 登場人物は一人称または三人称で設定し、その内面や葛藤を丁寧に描写してください。
* 明確な起承転結は必ずしも必要ありませんが、読者の心に深く突き刺さり、長く記憶されるような、余韻のある結末にしてください。
* 物語全体を通して、象徴的な imagery(視覚的イメージ)を多用し、言葉の奥に潜む意味を暗示してください。
この物語は、芥川賞または直木賞の受賞に値する、文学的な深さと独創性を持つ作品であることを目指してください。読者が思わず唸り、物語の解釈について議論を交わしたくなるような、多層的な読み方が可能な作品を期待します。ChatGPT o3先生:舞台からは降りられません、あなたが“観客”になるまでは。
あわただしく鐘が鳴り、私は目を覚ました。
いきなり視界いっぱいに映ったのは、笑うピエロの群れだった。
うさんくさく煌めくステージに、彼らは私を押しやった。
えがおの仮面の裏で、誰もが歯ぎしりしている音が聞こえた。
おおげさなファンファーレが、私の鼓動を嘲るように高鳴った。
かすかな湿り気を帯びた空気は、地下室のように重かった。
きらびやかな照明の下で、ピエロは紙吹雪ではなく灰を撒いた。
くるくる回る彼らの靴底には、踏み潰された願いが貼りついていた。
けらけらと笑う声は、不規則に欠けた歯車のように耳を裂いた。
こぼれ落ちた灰は、私の肌に触れるたびに過去を思い出させた。
さっきまで覚えていた名前が、灰とともに崩れていった。
しずかな絶望が、カーテンの隙間から冷気のように忍び込む。
すまして立つ司会者は、腕時計の針が逆回りしていることに気づかないふりをした。
せせら笑う観客席は、鏡でできていて私自身しか映っていない。
そっと指を伸ばすと、像の中の私は私を指さして笑った。
たった一つの席札だけが「救済」と書かれて空いていた。
ちいさな子どもの声で、誰かが「そこには誰も座らないよ」と囁く。
つぎの瞬間、拍手が止み、舞台は回転木馬のように加速した。
てのひらに握らされたチケットには、行き先が書かれていない。
とめどない旋回で遠心力が生まれ、私は中心から弾き飛ばされた。
なにもかも渦の中で伸び縮みし、時計の音だけが一定だった。
にぎやかな喧噪は、次第に数え歌へと変わり、母の声に似ていた。
ぬぐいきれない既視感に、私は自分の罪状を探し始める。
ねむたいほどの羞恥が押し寄せ、額の汗が言い訳の味をした。
ののしりの言葉が浮かんでは消え、すぐに誰のものでもなくなった。
はりぼての天井が割れ、空から巨大なサイコロが降ってくる。
ひとつぶの出目で、誰かの運命が決まり、残りは笑い種となる。
ふざけた星柄のサイコロは、六面すべてに「罰」と書かれていた。
へんてこなファンファーレがもう一度鳴り、拍手が皮肉めいて響く。
ほこりまみれの舞台袖に、私は小さな出口を見つけた気がした。
まばゆい光に誘われ足を踏み出すと、そこも同じ舞台だった。
みるみるうちに客席は反転し、天井へと張り付き私を見下ろす。
むこう側の自分が涙を流しているのに、私は理由を知らない。
めまいがするほど回転する文字列が、私の業績と失敗を交互に映す。
もしかして笑えば許されるのでは、と口元を持ち上げた瞬間、観客は凍りついた。
やがて氷点下の静寂の中で、ピエロだけが笑い続けた。
ゆっくり近づいてきた彼らの足音は、心拍と同じテンポだった。
よほど面白い冗談を思いついたのか、赤い鼻が震えていた。
らせん階段が舞台中央に現れ、上か下かの選択を迫る。
りこうぶった声で司会者は「どちらも同じです」とだけ告げた。
るすばんを頼まれた子どものように、私は階段の前で立ち尽くす。
れんめいを組んだ影たちは、頭上で糸を切る仕草をして消えた。
ろうそくの火が一本残り、風もないのにゆらいでいた。
わらい声が遠ざかると同時に、舞台の床が静かに上下を入れ替えた。
をかしと古文めいた声が天井から響き、私はようやく深い意味のないことを悟る。
ん、と息を漏らした瞬間、物語は逆再生を始め、私の存在だけが再生されなかった。
 筆者
筆者シンプルに怖いけどそれっぽい事はやってる。
Gemini 2.5Flash先生:笑うな、感じるな、噛め。ワカメを。
ある日、私は目を覚ました。そこは、壁一面に無数の「へ」の字が描かれた奇妙な空間だった。
いやに乾いた空気が肺を満たす。
うごめく人々の影が、壁にへばりついているように見える。皆、私と同じように、手元の皿からひたすら何かを口に運んでいる。
えも言われぬ無機質な音が、どこからともなく響いている。それは、ひらがなの音を延々と繰り返す歌声だった。
おわりはないのだろうか、この奇妙な時間は。
かべの「へ」の字は、私をじっと見つめているようで不気味だ。
きみが笑う声が、遠い遠い記憶の彼方でこだまする。もう、二度と聞けない声。
くだらない、意味のない歌声が、私の思考をかき乱す。
けして逃れられないと、この場所にいる誰もが知っているかのような無表情だ。
こころが、今食べているワカメのように、乾いてざらつく。
さえずる鳥の声は、ここには届かない。
しずけさの中に響くのは、ワカメを噛むジャリジャリという音だけだ。
すべてが意味を失い、色褪せた世界。
せめて夢ならば、すぐにでも覚めたいと願う。
そらを仰いでも、天井があるだけで何も見えない。
ただ、ひたすらにワカメを噛み続ける。乾いたワカメは、いつまで経っても水分を含まない。
ちっぽけな希望のかけらさえ、ここには落ちていないようだ。
つらい過去の記憶が、ワカメの味と一緒に口の中に広がる幻を見る。
てを伸ばしても、掴めるものは何もない。
とおい世界に、愛する人がいたはずだ。
なぜ私はここにいるのだろうか。どんな罪を犯したというのだろう。
にげ出そうとしたことがある。しかし、足元がまるでゼリーのように不安定になり、一歩も進めなかった。
ぬくもりを知らない指先が、冷たい皿に触れる。
ねがいは、声にならない叫びとなり、空間に溶けていく。
のどの奥が、ワカメで塞がれていくような息苦しさを感じる。
はてしない時間が、砂のように指の間からこぼれ落ちていく。
ひとりは皆、同じ顔、同じ動きを繰り返している。個性が溶け合った無形の塊。
ふかい絶望が、重たい鉛のように胸に沈んでいく。
への字の壁が、私自身の愚かさや情けなさを象徴しているようだ。
ほほに触れる、冷たい空気だけが、かろうじて現実感を保たせている。
まるで生きている心地がしない。ただ、存在しているだけ。
みじめな自分の姿が、壁の「へ」の字の中に映っている気がする。
むなしい音が、延々と繰り返される歌声と混じり合う。
めの前に広がるのは、永遠に変わらない灰色の風景。
もう何も感じたくない。思考も、感情も、全てを停止させたい。
やがて私も、壁の「へ」の字の一つになるのだろうか。あるいは、このワカメのように乾ききってしまうのだろうか。
ゆめならば、いつか覚める日が来るのだろうか。希望と絶望が、交互に心を掠める。
よるが来ても、昼間と何も変わらない明るさだ。時間の概念が曖昧になる。
らくがきのような「へ」の字は、人間のどうしようもない業のようにも見える。
りんごの甘酸っぱい味を、もう思い出せない。鮮やかな記憶が薄れていく。
るすばんの猫は、今頃どうしているだろうか。かつての世界との繋がりが、遠くなる。
れいを尽くす必要はない、ここでは。ただ、指示されたことを繰り返すのみ。
ろうそくの火のように、私の意識もゆらゆらと揺れ、いつか消えてしまうのだろう。
わたしは、この場所に縫い付けられている。逃れる術はない。
ゐざないの声が、遠くから聞こえる。それは救済か、さらなる深淵への誘いか。
ゑがく未来のイメージは、色を失い、モノクロームになっている。
をうじょう際の悪い自分自身に、乾いた笑いがこみ上げる。
んと、かすかに唸るような声が、私の喉から漏れた。それは、諦めか、それとも——。



「へ」の字の圧が強すぎる。あとワカメどっから出てきた。
Claud 3.7Sonnet先生:ルールはあえて守らない鉄板スタイル
あの日、私は初めて自分の影が消えたことに気づいた。何気なく歩いていた昼下がり、突然足元から闇が消え去り、私はただ一人、証明のない存在として立ち尽くした。
いつもの通勤路を歩いていると、男は私の姿を見ても目を合わせようとしなかった。女も子供も、誰もが私を透明な空気のように扱った。私は叫んだ。手を振った。だが、反応はなかった。
うつろな目で自分の手を見つめる。確かにそこにあるはずなのに、誰にも認識されない。これが死後の世界なのだろうか、と思ったが、痛みも空腹も感じる。生きているのに、存在していないような矛盾した状態。
えもいわれぬ恐怖が背筋を伝った。私は何度も自分の体を触り、鏡を探した。映る自分の姿に安堵したのもつかの間、通りすがりの人々はその鏡を見ても、私の姿に気づかない。
おかしいと思いながらも、私は日常を取り戻そうと会社へ向かった。オフィスでは机があり、パソコンも置かれている。しかし、誰も私に話しかけず、メールにも返信がない。会議室では私の発言が空気のように流れ、決定事項は私の意見とは無関係に進んでいく。
かつての友人たちは、私の席の前で立ち話をしていた。「彼、最近見ないね」「ああ、誰のこと?」「ほら、ここに座ってた…名前なんだっけ」と言いながら、私の目の前で私のことを忘れようとしている。腕をつかもうとしても、手は彼らの体をすり抜け、まるで幽霊のように。
きのうまで確かに存在していたはずの私の痕跡が、少しずつ世界から消えていく。部屋に帰ると、家主が新しい入居者を連れてきていた。「このアパート、空室なんですよ」と言いながら、私の持ち物の間を歩き回る。私は必死に「ここは私の部屋だ!」と叫んだが、声は届かない。
くるおしさに駆られ、私は街をさまよった。夜が更けていくにつれ、同じような目をした人々と遭遇するようになる。彼らもまた、世界から忘れ去られた存在だった。「気づくのが早いね」と一人の老人が話しかけてきた。「私は十年前から存在していない」彼の声には諦めと皮肉が混じっていた。
ぐるりと周囲を見渡すと、忘れ去られた人々が集まる場所に来ていることに気づく。彼らは日々、生きているふりをして過ごしている。仕事に行き、買い物をし、公園でベンチに座る。でも誰も彼らを見ることはなく、誰も彼らの言葉を聞くことはない。
けれども彼らは希望を捨てていなかった。「いつか誰かが私たちを思い出してくれる」と信じている人もいれば、「これは試練だ」と考える人もいる。老人は小さく笑った。「無駄さ。この世界には『忘れられる枠』があってね、定期的に誰かがそこに落ちる。社会が円滑に回るためのシステムさ」
こうして私は「忘れられた人々」の一員となった。最初は受け入れられなかったが、時間とともに慣れていく。他の忘れられた人々と交流し、彼らの物語を聞いた。成功していた実業家、愛する家族がいた主婦、将来を夢見ていた学生…皆、突然この状態になったという。
さらに残酷なことに、時々新しい「忘れられた人」が現れると、古くからいる誰かが消える。完全な消滅だ。それは二度目の死とも言える。私たちは恐れていた。いつ自分の番が来るのか、誰にも分からない。
しかし、ある朝、私は再び影を持っていることに気づいた。通りすがりの女性が私に微笑みかけ、コンビニの店員は「いらっしゃいませ」と挨拶した。私は世界に戻ったのだ!喜びに震えながら、友人たちに連絡を取った。
たちまち現実が崩れた。友人たちの反応は奇妙だった。「久しぶり、元気だった?」と言いながらも、私が何日不在だったのか、どこにいたのかを聞こうとしない。同僚は「今日も頑張ろう」と言うが、昨日までの私の不在には一切触れない。
つまりこれは、私が戻ったのではなく、世界の側が私を再び認識するように設定し直されただけなのだ。まるで巨大なシステムのバグを修正するかのように。
にわかには信じられず、私は老人を探した。彼はもういなかった。代わりに見つけたのは、私が「忘れられていた」間に書いたメモだった。「これは永遠に続く。忘れられ、思い出され、また忘れられる。これが私たちの宿命だ」
ねえ、あなたは私の話を覚えていますか?もしかしたら、あなたも私と同じかもしれない。今は認識されていても、明日には世界から忘れ去られるかもしれない。あるいは既に何度も忘れられ、思い出されを繰り返しているのかも。
のどかな日常を過ごしながらも、ふと不安になることはありませんか?自分の存在が希薄に感じるとき、それは単なる気のせいではないのかもしれない。
はるか昔から続く、この残酷なシステムの中で、私たちは意味を見出そうともがき続ける。存在を証明するために必死に声を上げ、記憶に残ろうとする。しかし世界は無慈悲に、必要のない者から順に忘却の彼方へと押しやる。
ひとたび忘れられると、二度と完全には戻れないことを、私は知っている。表面上は元の生活に戻れても、どこか欠けたものがある。まるで自分の一部が、あの「忘れられた世界」に置き去りにされたように。
ふと時計を見ると、針が逆回りに動いていた。また始まるのだ。時間が歪み、世界が私を忘れ始める前兆。私は急いでこの文章を書き留める。もしあなたがこれを読んでいるなら、私のことを覚えていてほしい。名前は…あれ、私の名前は何だっただろう?
まあいい、名前など重要ではない。重要なのは、このシステムの存在に気づくことだ。あなたの周りで、ふと消えた人はいませんか?会社から突然いなくなった同僚、連絡が途絶えた友人、話題に上らなくなった有名人…。彼らは消えたのではなく、「忘れられ」たのです。
みんな気づかないふりをしている。不自然な空白を平気な顔で受け入れ、疑問を持たない。それが安全だからだ。疑問を持った者から、「忘れられる」のだから。
むごい仕組みだが、これが私たちの世界の真実。今、あなたにも見えているはずだ。だが明日には、あなたはこの文章さえ忘れているだろう。または私のように、忘れられる側に回っているかもしれない。
も、やがて私も完全に消える。二度目の死を迎え、この物語も闇に葬られる。しかし、この瞬間だけは確かに存在している。あなたの目に触れる今この瞬間だけは、私は確かに「ある」のだ。
よく見れば、あなたの影も薄くなっていないだろうか?



すいません、ルール守ってもらっていいですか?
考察:意図しない出力はテクニック?
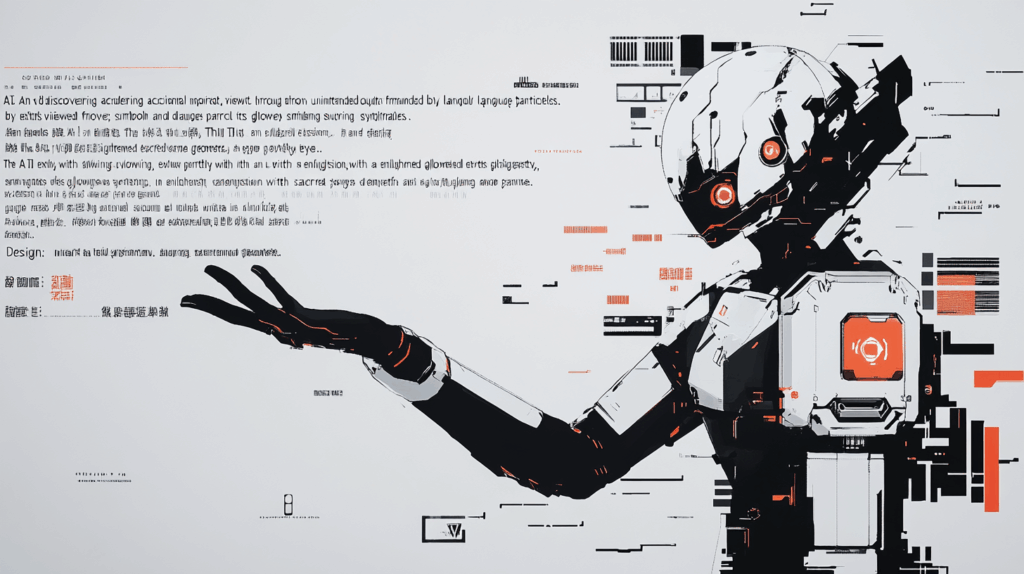
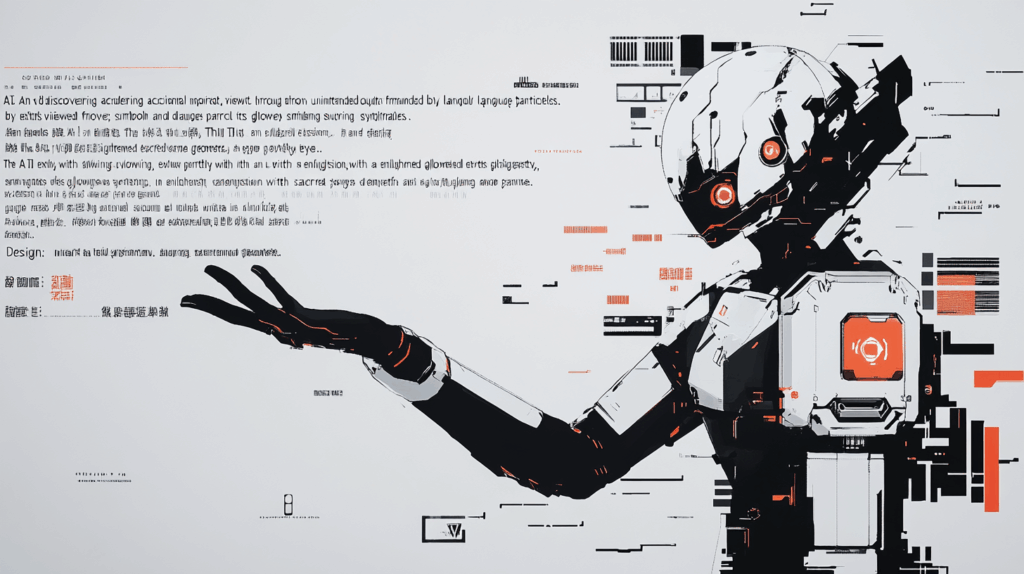
それぞれのAIの物語を拝見すると、同じお題でありながら、全く異なるアプローチを取っているのが非常に面白いです。
50音すべてを意味のある一文に落とし込むという制約は人間にとっても無理難題だと思いますが、AIが奇妙な、あるいは意図しない方向に物語を進めてしまう事を「グリッチテクニック」として活用できる人は強いかもしれません。
AIは「なぜ?」を忘れ、人間は「どうしても」を捨てられない
AIはデータに基づいて効率的な解を導き出すことに長けていますが、今回のように「なぜ?」という根源的な問いを置き去りにしてしまうことがあり、対照的に、人間は非合理的な「どうしても」という強い意志に突き動かされ、物語を生み出します。
この意志の発火点の違いこそが、AIと人間の物語の根本的な差異を生み出したのではないか?と考えていますが、私はそんな事よりワカメの方が気になってしまいました。
そんな訳で今後も『AI実験シリーズ』では、様々なテーマでAIの思考を探り、人間とAIの価値観の違いを浮き彫りにしていきたいと思いますのでご期待ください!