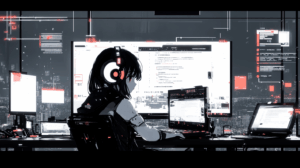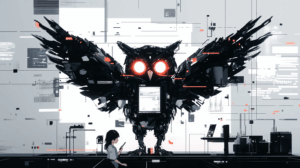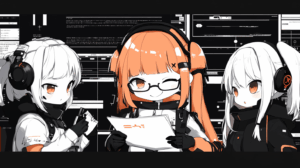著者:GOZEN AI Lab管理人
生成AIエンジニア(オープンバッジ取得)生活や業務に潜む「面倒くさい」を手放すため、生成AIを活用した業務効率化施策、自動化ワークフローの構築・運用などを手がけ、実践と継続的な改善を通じて仕組みづくりを推進している。
結論:5132文字の記事作成完了まで、2時間以内に終わる!
一般的な記事、特に5000文字を超えるような、ある程度の情報を網羅する記事となると、リサーチから執筆、校正、画像まで含めると、正直なところ数時間から半日以上かかることも珍しくありません。これは、多くのブロガーさんやライターさんが共通して抱える「時間」という大きな壁です。
この記事では、私が実際に約5132文字のブログ記事をテーマに、「一般的にこれくらいの文字数の記事を書こうと思ったら、どれくらい時間がかかるものなのか?」ということと、「私が自作したAI記事作成自動化ツールを使い始めた後、実際どれくらいの時間で書けているのか?」という、気になるBefore/Afterを、私の率直な感想と具体的な数値と一緒にお話しします。
さらに、実際に私が自動化ツールを使って記事を作成している風景を収めた動画も公開しています。このサイトでは全てAIを使用し記事を書いているのですが、皆様の記事作成の効率化、そしてサイト運営の可能性を広げる一助となれば嬉しいです。ぜひ、最後まで読み進めてみてください。
自動化で時間はどう変わった?リアル数値と動画公開
一般的な時間って、どれくらい?
先ほども触れたように、このくらいのボリュームの記事を、リサーチから構成、執筆、構成、画像選定まで全部自分でやろうとすると、一般的には数時間から半日以上かかるのが普通だと思います。集中して、カフェにこもって…なんてやっても、それくらいの時間は覚悟が必要ですよね。これは、多くのブロガーさんやライターさんが実感している「記事作成の壁」の一つだと思います。
私のBefore/After
下記が実際に5132文字の記事を仕上げてみた結果です。
- 【手動の場合(一般的目安)】5132文字の記事作成時間:数時間〜半日以上
- 【私が自動化ツールを使った場合】5132文字の記事作成時間:多くても2時間
一般的にかかる時間と比べると、劇的に時間が短縮できているのが分かります。もちろん、これはツールに「はい、全部お任せ!」って丸投げして、ポチッとボタンを押した時間ではないです。記事の構成を考えさせたり、生成された文章をチェック・修正したり、自分の言葉で加筆したり…という作業全部を含めて、「多くても2時間」です。
AI記事作成自動化ツールの「実際の様子」
「いやいや、本当にそんな早く書けるの?」って疑いもあるかとおもいます、なので実際の自動化ツールの挙動を見てもらい、記事生成→ワードプレスに張り付けるまでを動画に撮ってみました。
余談ですが、3記事まとめて作っています。これが100記事あっても作れます。
記事作成自動化、その具体的な手順
「自動化って言われても、具体的なイメージ湧かない」って思いますよね。私が今回、実際にやってみた流れを、ざっくりと説明します。使うツールによって細かい操作は違いますが、大まかなステップは同じです。
ステップ1:テーマとキーワードを決める
まず最初にやることは、書きたい記事のテーマや、読者に検索してもらいたいキーワードをスプシ等にまとめています。
動画の画面左下の部分ですね、これは皆さんすでに行っていると思いますが、ラッコキーワード等から「キーワード」を選定しています。
ステップ2:記事の設計図(構成)を作る
動画の画面右側の部分にあたります、ここで作成したワークフローをもとに、ツールが記事の構成案、つまり「各見出し、文中のキーワード、SEO(LLMO)対策、読んでほしい読者層にしっかり適切に内容がと伝わるか?ファクトチェック」等を、AIに指示を出します。ここが記事の「骨組み」で大事な要素なので、日々改善と更新を行っています。
また、見出しをつけたり、太字にしたり、箇条書きにしたりもこの段階で自動で行うように指示しています。
ステップ3:本文のベースを生成
構成案が決まったら、それぞれの見出しの下に書く本文をツールに生成してもらいます。AIのモデルや好みにもよりますが、私はGemini2.5Flashを使用しています。
ステップ4:確認と修正
ツールが書いてくれた文章をそのまま使う事はありません、AIは必ずしも正しい事を書くとは限らないので、必ず「品質、変な言い回しはないか、私の伝えたいニュアンスになってるか」等を、よくチェックします。そして、ツールには書けない「自分らしさ」を加えていきます。ここが一番時間を使うステップですが、ツールがあるからこそ、この「仕上げ」にじっくり時間をかけられるようになりました。
ステップ5:読者が読みやすいように仕上げる
読者の人が読みやすいように見た目を整えます。写真やイラスト等もこのフェーズで入れます。
私の場合、画像はブランディングイメージを崩さないようにする為に、全てMidJourneyを使用して画像生成を行います。ここは好みだと思いますので参考までに。
正直レビュー!記事作成自動化の「良いところ」と「気になるところ」

実際に、「これはすごい」と思うメリットと、「ここは気をつけないと」と感じるデメリットをお話しします。
メリット
- 時間!とにかく時間がない人に福音!:これがもうダントツです。一般的にかかる時間と比べて、私の時間は「多くても2時間」に収まりました。生まれた時間で、他の記事を書いたり、別の仕事をしたり、趣味に使ったり…自由な時間が増えるのは最高です。
- 「書けない…」の壁が低くなる:画面を前に「何書こう…」ってフリーズすること、ありますよね?ツールが構成案や文章のベースを作ってくれるおかげで、書き始めのハードルがグッと下がり「叩き台がある」という安心感が全然違います。
- 自分だけじゃ思いつかない視点:ツールが色々な情報を引っ張ってきてくれるので、「そういう書き方もあるのか」「こんな情報もあったのか」という、自分一人で考えてたら気づかなかった視点や情報を取り入れられることがあります。
- 数をこなせるようになる:記事作成にかかる時間が減るという事は、同じ時間でも書ける記事の数が増えるという事です。ブログ全体の記事ボリュームを増やしたい人には最適だと思います。
デメリット
- 「これ、本当に合ってる?」情報の確認は絶対!:AIが生成する情報は、たまに間違っていたり古かったりする事があります。なので、「ツールが書いたからOK!」ではなく、自分で必ず内容をチェックし、正しい情報か確認する手間は必要です。ここをサボると、読者に間違った情報を伝えてしまうリスクがあります。
余談ですが、リライトのツールも作ってしまい、月次更新も自動化させてしまえば良いですね。 - 「なんか、どこかで読んだことあるかも…?」オリジナリティ問題:ツールが学習したデータから文章を作ってるので、しっかりとシステムプロンプトを組まないと他の記事と似たような表現になってしまうことがあります。「いかにもAIが書きました」という感じの、味気ない文章になりやすいです。なので、必ず自分の言葉で書き直したり「あなたらしさ」を出す工夫がすごく大事になります。
- ツールの使い方に慣れが必要:効果的にツールを使うには、「どういう指示を出せば、自分の欲しい答えが返ってくるか」を掴むまで、少し練習が必要です。最初は何回か「うーん、ちょっと違うな」って思うこともあるかもしれません。改善を繰り返しましょう。
- 感情や、細かいニュアンスはやっぱり人間じゃないとダメ:人の気持ちに寄り添うような、感動させるような、ユーモアのあるような…そういう人間ならではの感情とか、微妙なニュアンスを文章で表現するのは、今のAIにはまだ難しい部分だと思います。読者の視点に立ち、読者の気持ちを考え、しっかりと伝える文章にする事が鍵です。
まとめ:「AI×人間」の記事作成スタイル
ここまで読んでいただけている方には「ツールを使えば何でもOK」というわけではない事をは伝わっているかと思います。ツールは素晴らしい文章のベースを作ってくれますが、そこに血を通わせ、命を吹き込むのは、やはり人間、つまり書き手です。
ツールが情報収集や文章生成の「速さ」を提供してくれるなら、私たちは自分の「頭」と「心」を使って、記事に深みや共感を生み出す。これからの記事作成は、AIと人間がそれぞれの得意な部分を活かし合う、「二人三脚」スタイルが主流になっていくんじゃないかな、と私は感じています。
私も、AIツールを使いながら「読んでよかった!」って思えるような、価値のある記事をもっともっと生み出していきたいと思っています。私の体験が、皆さんのブログ運営や文章を書く際のヒントになれば幸いです。
よくある質問:FAQ
Q1. 記事作成自動化ツールを使えば、全く文章を書かなくてよくなるの?
A1. いいえ、完全にゼロになるわけではありません。ツールはあくまで文章作成の「下書き」や「叩き台」を作ってくれるものです。生成された文章の確認、修正、加筆、そしてあなたのオリジナリティを加える作業は、人間が行う必要があります。今回の私の例でも、「多くても2時間」はその確認・修正の時間も含んでいます。
Q2. AIが書いた記事はSEOに不利なの?
A2. AIが生成しただけの、他の記事と内容が重複していたり、情報の正確性が低かったりする記事は、SEOにおいて評価されにくい可能性があります。重要なのは、AIをツールとして活用しつつ、読者の検索意図にしっかりと答え、オリジナリティや信頼性(E-E-A-T)を加えることです。
Q4. AIツールで生成した文章の著作権はどうなるの?
A4. 現在、AIが生成した文章の著作権については法的な整備が追いついていない部分があり、明確な国際的な取り決めはありません。ただし、多くのAIツールの利用規約では、生成されたコンテンツの所有権はユーザーにあるとしている場合が多いです。念のため、利用規約を確認することをお勧めします。
専門用語解説
- SEO (Search Engine Optimization):検索エンジンの最適化のこと。Googleなどの検索エンジンの検索結果で、自分のウェブサイトや記事を上位に表示させるための様々な取り組みを指します。読者が知りたい情報を提供し、使いやすいサイトにすることが重要視されます。
- E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness):Googleの検索品質評価ガイドラインで重要視されている要素です。「経験」「専門性」「権威性」「信頼性」の頭文字を取ったもので、特にYMYL(Your Money or Your Life)と呼ばれる人々の健康やお金に関わる重要な情報においては、このE-E-A-Tが高い情報が上位表示されやすい傾向があります。
- AI記事作成ツール:AIの力を使って、文章を書くお手伝いをしてくれるパソコンソフトとかウェブサービスのことです。与えられたキーワードとかテーマを入力すると、ブログの記事だったり、メールの文章だったり、色々な種類の文章のベースを作ってくれます。