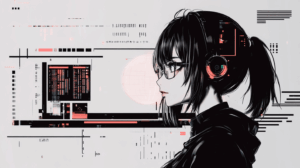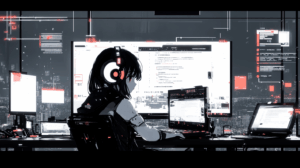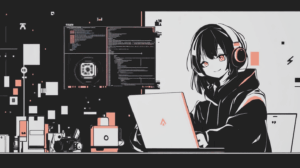著者:GOZEN AI Lab管理人
生成AIエンジニア(オープンバッジ取得)生活や業務に潜む「面倒くさい」を手放すため、生成AIを活用した業務効率化施策、自動化ワークフローの構築・運用などを手がけ、実践と継続的な改善を通じて仕組みづくりを推進している。
結論:スマホの充電に例えると、「API」と「MCP」はわかりやすい説!
インターネットで何かを調べたり、スマホでアプリを使ったり、オンラインで買い物をしたり。その裏側では、様々なシステムやサービスが連携して動いています。この連携に欠かせないのが、今回テーマである「API」と「MCP」です。
この記事では、「APIとMCPって具体的に何が違うの?」「なぜ一緒に話題になることが多いの?」「私たちの生活とどう関係があるの?」といった疑問に、専門知識がない方でもスッキリ理解できるよう、分かりやすい例え話を交えながら解説していきます。
この記事を読めば、APIとMCPの役割や関係性が分かり、普段使っているサービスの仕組みが少し違って見えるかもしれません。ぜひ最後まで読んでみてください。
APIとMCPとは? スマホの充電とマルチケーブル
APIって何?──スマホごとの「充電ルール」と「差込口」のこと
普段スマホを充電するとき、iPhoneならLightningケーブル、AndroidならUSB-Cケーブルを使いますよね。
これ、実はスマホごとに「充電のルール」と「差込口」が違うからなんです。
- iPhone:Lightningという専用の差込口と「Lightningなら充電OK!」というルールを使っている
- Android:USB-Cという別の差込口と「USB-Cなら充電OK!」というルールを使っている。
この「差込口+ルール」が、ちょうどAPIにあたります。
つまり、API=システムが外のサービスとやりとりするための「ルール」と「接続口」という事です。
iPhoneならLightningのAPI、AndroidならUSB-CのAPIを使って、外部サービスから機能を受け取っているイメージですね。
MCPって何?──バラバラな充電ルールをまとめる「マルチケーブル」
よくある困った場面を思い浮かべてください。
「Lightningケーブルしかないけど、Androidスマホを充電したい!」
「USB-Cケーブルしか持ってないけど、iPhoneを充電したい!」
こんなとき、変換アダプターや、マルチタイプの充電ケーブルを使いますよね。
実は、これがまさにMCPの役割なんです。
- MCPは、iPhoneのLightningも、AndroidのUSB-Cも、ぜんぶ理解できる。
- そして、それぞれの形にピッタリ合わせて、きちんと接続してくれる。
要するに、MCP=バラバラなAPIをまとめて、どんなシステム同士でもつなげてくれる「マルチケーブル」なんです。
たとえば、本来なら直接つながらないような異なる会社のシステムも、MCPを通せばスムーズに連携できるようになります。
「充電できない!」って困ることがなくなるイメージですね。
私たちの身近にあるAPIとMCP
APIとMCPは、専門的な技術のように聞こえるかもしれませんが、実は私たちの日常のすぐそばにあります。
スマートフォンは、まさにAPI連携の塊のようなものです。例えば、Facebookアプリが写真に位置情報をつけるためにスマートフォンのGPS機能のAPIを使ったり、様々なアプリがプッシュ通知を受け取るためにOSのAPIを利用したりしています。アプリ自体は個別のサービスですが、OSが提供するAPIを通じて、他のサービスと連携しているのです。これは、ある意味でOS全体が様々なアプリを動かす「MCP」のような役割を果たしているとも言えます。
また、オンラインサービスでもAPIは当たり前のように使われています。「他サービスのアカウントでログイン」機能は、サービス間のAPI連携によって実現されていますし、Webサイトに埋め込まれた地図や動画も、それぞれのサービスが提供するAPIを利用しています。
企業においては、デジタルトランスフォーメーション(DX)を進める上で、既存の様々なシステムを連携させることが重要になります。ここでAPIがシステム間の「つなぎ役」となり、それらを一元的に管理・運用する基盤としてMCPの考え方が活用されています。これにより、業務効率化や新しいサービス開発が可能になります。
APIとMCPがもたらす未来

APIとMCPは、これからのデジタル社会を築く上でますます重要になっていくでしょう。
APIが「つなぐ」ことで、これまで単独で動いていたサービスやデータが連携し、新しい価値を生み出しやすくなります。例えば、様々な企業のサービスAPIを組み合わせることで、革新的なアプリケーションやビジネスが生まれています。
そして、MCPが「まとめる」ことで、複雑になりがちなシステム全体を効率的に、かつ安全に運用できるようになります。これは、企業だけでなく、都市全体のインフラ管理やエネルギーマネジメントといった分野でも応用が進んでいます。
APIとMCPは、個々のシステムをより賢く、全体をより滑らかに動かすための両輪と言えるでしょう。これらの技術の進化は、私たちの生活をさらに便利で豊かなものにしてくれる可能性を秘めています。
まとめ
この記事では、「API」と「MCP」について、初心者の方にも分かりやすいように解説してきました。
今後、さらに多くのサービスがAPIを通じて連携し、それらを効率的に管理・運用するMCPのような仕組みが発展していくでしょう。AIエージェント等でワークフローを作っている人は特に、APIとMCPは知っておきたい基本的な概念と言えます。
よくある質問:FAQ
Q1. APIとMCPはどちらか一方だけあればいいですか?
A1. いいえ、多くの場合、両方が重要です。APIは個々のシステム間の連携を実現する「部品」のような役割、MCPはその部品を使って全体を効率的に動かす「司令塔」のような役割です。全体を管理(MCP)するには、各部品(システム)と適切に連携(API)できる必要があるからです。
Q2. MCPは具体的にどんなシステムに使われていますか?
A2. 企業の情報システム(複数の業務システム連携)、クラウドサービス管理、IoTデバイス管理、工場の自動化システム、スマートシティのインフラ管理など、複数の異なる要素をまとめて制御・監視する必要がある様々な分野で活用されています。
Q3. APIを使うとどんなメリットがありますか?
A3. APIを使うと、ゼロから全てを作る必要がなくなり、既存の他のサービスや機能と簡単に連携できるようになります。これにより、新しいサービスを素早く開発できたり、既存のサービスをより便利に拡張したりすることが可能になります。例えば、地図APIを使えば、自分で地図システムを開発しなくても、自社サービスに地図機能を組み込めます。
Q4. プログラミングの知識がなくてもAPIやMCPに関わることはありますか?
A4. はい、あります。例えば、WordPressのようなCMSでプラグインを追加する際に、プラグインが他のサービスと連携するためにAPIを使っていることがありますが、ユーザーはAPI自体を意識しません。また、クラウドサービスの管理画面(これがMCPの一種と言えます)を使って、複数のサーバーやサービスを一元管理する場合も、必ずしもプログラミング知識は必須ではありません。ただし、開発や運用に関わる場合は、ある程度の知識が必要になることもあります。
専門用語解説
- システム連携: 複数の独立した情報システムやサービスを接続し、互いにデータや機能をやり取りできるようにすること。APIはシステム連携を実現するための主要な手段の一つです。
- デジタルトランスフォーメーション (DX): 企業がデータとデジタル技術を活用して、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、組織や企業文化、風土をも改革し、競争上の優位性を確立すること。APIやMCPはDX推進に不可欠な技術基盤となります。
- クラウドサービス: インターネット経由で、コンピューティング資源(サーバー、ストレージ、ソフトウェアなど)を利用できるサービス。クラウド環境では、APIやMCPの技術が高度に活用されています。
- OS(オペレーティングシステム): コンピュータやスマホを動かすための基本ソフトウェア。たとえば、Androidはスマホ用のOS、Windowsはパソコン用のOS、MacはmacOSという独自のOSを使っています。それぞれがハードウェアとアプリの橋渡しをしていて、APIを通じてアプリがシステムの機能を利用できるようになっています。